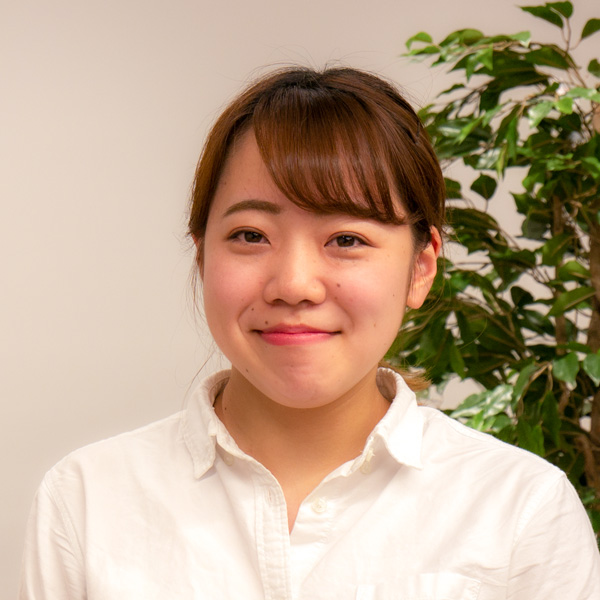データを活用した人材育成・営業力強化
- 新しい行動様式が変わり、デジタル化の波が押し寄せています。結果として新しい営業スタイルへシフトが進んでいます。営業は会社の売上につながる日々の活動を勤しんでおり、とても重要な役割を果たしています。
- 一方で営業組織に関するテコ入れも始まっており、育成やイネーブルメンとに注目が集まっています。本記事では育成・イネーブルメントの重要性、事例について触れ、なぜ取り組むべきかについて触れていきます。
- 最終的に強い組織を作るためには、人材育成についてどのようなステップで進めるかについて触れ、自社にとって必要なスキルを持つ社員の採用や育成を強化していくことが重要性をご理解いただけると幸いです。
営業を取り巻く環境は大きく変化している
オンライン商談が当たり前に
外部環境の変化により、客先に出向く訪問営業からオンラインなどの非対面営業の比率が大きくなっています。これまでは当たり前だった訪問営業ができなくなっても、企業の営業活動自体は継続させなければなりません。
結果として、企業間の BtoB ビジネスの世界では必然的にオンライン商談が推奨されスタンダードになっています。
リモートワークの常態化
オンライン商談において、当初は馴れない面もありましたが、働き方の柔軟性や、移動時間の削減、家族との過ごす時間が増えるなど、多くのメリットがあることが評価されています。メリットばかりではないもの、外出自粛などの環境変化でリモートワークが常態化しているのが実情です。
The Model化が普及し、分業とデータ活用が必須に
The Model型の営業組織を取り入れる会社も増えてきています。営業プロセスを分業制にすることで各部門が専門的な役割を果たし、日々の活動記録を残しデータを蓄積させ
ています。そのデータを振り返り、営業活動の改善を行い、顧客への最適なアプローチができるようPDCAを回しているのです。
SaaSが台頭し、様々なツールを組み合わせて使う時代に
SaaS ( Software as a Service ) とは自社に必要なソフトウェアの機能を必要な分だけ契約し、自社のサービスに取り入れる形態です。自社にとって不足している機能は何かを見極め導入ができ、大掛かりなシステム投資が発生しないのではじめやすいというメリットがあります。
SFAやMA、あるいは名刺管理ソフトなど、様々なソフトウェアを導入し、レゴブロックを組み上げるよう、自由に自社サービスを拡充し、営業組織を強化できる柔軟性があります。
インサイト営業の重要性の拡大
インサイトとは洞察という意味ですが、営業活動においては「購買意欲のポイント」というニュアンスになります。営業活動がThe ModelやSaaSを踏まえ、これまで以上に科学的にアプローチができるようになり、データも貯まってきています。
したがって、そのデータから顧客が購買意欲を感じるポイントを見出し、適切なアプローチを仕掛けられるかが成約率向上のキーとなり、重要性が増しています。
質的な意味でも、量的な意味でも営業力不足
従来の先発完投型の営業スタイルから、分業制の営業スタイルのニーズが増していることで、営業活動において関連するメンバーも増え、専門性も増しています。
また、顧客の購買プロセスも変化しており、顧客を理解するためにはこれまで以上に試行錯誤が必要になります。
結果として質量とも営業力が必要になり、会社としても投資すべき重要なポジションとなっています。
加えてコロナ禍によりリモートワークが当たり前に
営業形式は対面営業から非対面営業へ
営業活動を取り巻く環境が変化していることに加え、コロナ禍により、従来の対面営業の割合が著しく減っています。反面、リスクを最小限にするために非対面のオンライン営業が採用されています。
営業活動は量から質へ
オンラインの営業活動が取り入れられ変化が起きていますが、営業活動における成果は変わらず求められます。ただし従来の対面営業の訪問数や活動量で評価される営業から、効率的に結果を出せるような質の高い営業活動が求められています。
情報共有の仕組みはアナログからデジタルへ
営業活動が対面から非対面へシフトしているように、アナログで行ってきた営業活動や顧客管理がデジタル移行しています。デジタルで管理することで営業活動のデータが蓄積され、情報共有もしやすく、さらに分析もしやすくなります。結果としてデジタルへシフトすることで再現性の高い営業活動ができるメリットがあります。
結果、商談の実行に大きな変化
商談情報/ニュアンスの共有
オンライン商談では、画面越しの相手の反応が見えづらいことが多く、五感を使ったやりとりが難しくなっている売り手がニュアンスでなんとかすることができないので、売り手がきっちり用意する必要があります。
対面商談の場合、営業は上司とメンバーが一緒に活動をしながら訪問や商談など全ての質を高めることができました。しかし、現在の非対面商談では微妙な顧客の一呼吸の間や、現場のピリピリした雰囲気、提案時の反応や手応えなど、手に汗握る臨場感は画面越しでは限界があります。
基本的にはオンラインで商談が行われますが、ここぞというときや、対面でなければならない場面では、無理のない範囲で対面の打ち合わせのセットも打診してみるといいでしょう。
オンライン商談がメインでも、対面商談時には検温や換気、パーテーションで区切り、メンバーも人数制限するなど工夫はできるはずです
生産性のない社内向けの情報整備
社内向けの情報整理をしないと商談情報をきちんと共有できない、という課題を抱えている営業組織があります。報告のための情報整備など、対顧客以外の時間に営業活動が割かれていては、質の高い営業活動はできません。
SFAなど、効果的な情報整備をしていない場合、なぜこんなことをやる必要があるのか、という営業メンバーからの不満の声も上がるようになり、組織全体の士気の低下にもつながります。
社内向けの情報整備は最小限にできるよう、ルールを決め、できるだけ顧客との対話や提案の質を上げるための準備に時間を費やせるような体制を取ることが重要です。
顧客折衝
先ほど少し触れましたが、顧客との折衝のやり方も変わってきました。急に完全オンラインになったことで今までと異なる顧客との接し方に慣れなければなりません。
オンラインになったことでメリットは多数ありますが、顧客の温度感を感じながらの臨場感のある交渉は難しくなりました。オンラインになり、移動時間がなくなってできたことで接触回数を増やしたり、その分顧客の分析や提案準備に時間を割き、工夫して顧客折衝に臨んでいくことが求められます。
見えないモチベーション
これまで顔を合わせていた社員とのコミュニケーションが減ったことで、部下がサボっているのではないかという不安を感じるマネージャーも出てきています。
部下全員の動きを把握することは困難で、コントローラブルではないため、パフォーマンスが明らかに下がっている社員へのフォローも必要になってきます。
電話や定期的な面談を通し、コミュニケーションを取るなどして、部下のモチベーション管理を定期的に行いましょう。
営業の中でも育成に大きな課題感を持った企業は多い
営業組織を強化する上で、営業メンバーのスキルの向上、育成に関心があると応える組織は大多数存在します。採用に力を入れるのはもちろんですが、在籍している社員をどう育てるかが、ビジネスを伸ばす上で大きなポイントです。
理由として、人材は流動的なため、常に採用で自社のニーズに合う社員を探すことはできないですし、採用面接を受ける側も、数ある選択肢の一つとして面接を受けています。優秀な人材ほど入社までのハードルが高いため、そうであれば、カルチャーや人となりを知っている自社社員に活躍してもらえるよう、投資をする方が効率的といえるでしょう。
会社として強化したいポイントは「新規顧客の開拓」「営業プロセスの見直し」「営業・マーケティング戦略の策定・改善」が上位に来ています。アンケート結果から言えることは、多くの会社が営業組織の改革、強化に興味があるのです。
裏を返すと、まだまだ経営層は自社の営業組織を物足りないと思っており、改善の余地の可能性を感じ、頑張って欲しいという期待をしています。
営業組織、マネージャー、メンバーの育成やスキル向上に注目が集まっており、どのように効果的に能力を伸ばすのかという方法についても様々な研究が進められ、先進的な会社では成功事例も出始めています。
「会社の強化したいポイント/課題」に関するアンケート調査概要 ・有効回答数:1106名 ・データ集計期間:2019年1月10日~6月27日 ・調査対象:ソフトブレーン主催のセミナー参加者
育成・セールスイネーブルメントの効果
生産性、リードタイム、パイプライン、夫々で効果がある
セールスイネーブルメントとは日本ではまだ馴染みの薄いことばですが、「営業活動( sales )を継続的に結果をあげることを目的とした、営業組織の強化・改善( enablement ) のための取り組み」を指します。営業研修という言い方が一般的ですが、より具体的に科学的にデータに基づき売り上げを伸ばすためにどうしたらいいかにフォーカスしているというニュアンスで理解いただくと良いでしょう。
セールスイネーブルメントは生産性やリードタイムやパイプラインを
向上させることに具体的に効果があります。
営業活動を分解し、営業プロセスの細かい部分に踏み込み、日々の営業活動を改善するための総括的な取り組みだからです。
アンケートよりTrends Report – Quark
企業の取組み事例
事例:Open House
Open House社は営業に特に強みを持っている会社です。その営業組織を最大限に効果を発揮できているのは、IT部門が要因となっています。
例えば営業メンバーの行動を可視化し分析し、売れている営業の共通点を導き出しツールに反映しています。また、営業が日々の活動を進めやすくするための工夫が反映され、営業組織が楽になるため、IT部門が寄り添い、機能を反映させています。
結果として営業メンバーはSFAやCRMツールにデータを記録する癖ができ、営業活動の記録が残り、可視化、分析を行い、IT部門が改善を反映するという好循環を生み出しています。
また、内製と外製を組み合わせた営業組織のITシステム活用を徹底し、顧客に寄り添った提案のための営業ノウハウの共有を実現できているのです。
何も研修をすることが最善策ではなく、営業組織をリアルタイムにモニタリングし、どうしたら売上が向上する活動を最短距離で取れるか、という視点で協業ができているのです。
IT部門はドラえもん!? 営業とIT部門が良好な関係を築くオープンハウスの徹底的な現場主義とは
事例:NTTコミュニケーションズ
平均年齢46歳と平均年齢が高く、40代が2割、50代が8割の組織で、これまではそれぞれの営業が自分の営業手法やこだわりを持っていた。
SFAを導入したものの、単なる受注管理マシーンになっており、商談状況や活動管理は全くできていませんでした。
そんな折組織編成があり、新規開拓および新規商材を取り扱わなければならず、営業活動の見える化に取り組む必要に迫られました。
SFAとMAの導入、そして営業活動の記録を取り続けるように徐々に組織を改編していき、データを元にした再現性のある営業組織への取
り組みを行ってきました。
ただし、データは部門ごとに縦割りでしか活用されておらず、人材育成に関するデータは育成のみ、提案活動に至るデータは顧客情報にのみ利用されていました。
少しずつ状況を改善していき、データの有効活用をはじめ、これらの取り組みは徐々に評価されはじめました。ついに評価が認められ、トップの後押しで全社に展開されるようにもなり、データを元に再現性のある売り上げを上げる活動に活かされていきました。
イネーブルメント最先端事例!NTTコミュニケーションズの営業改革をリードするData.Campとは
事例:ベーシック
当初は受注率が1割を切るという大変厳しい状況だったが、セールスイネーブルメントを取り入れ、営業組織を改善していくことで受注率が2.5倍に改善されました。
当社は組織としてどのような成果をあげたいか明確にし、そのためにはどんなスキルを持った人材が必要かを落とし込んで行きました。
結果、組織の中で必要なスキルを可視化し、そのスキルを補うような育成プログラムを組み始めました。知識やスキルを身につけていくことで、できることが増えていき、それが行動に現れ、求めていた成果につながるようになったのです。
受注率2.5倍に!ベーシックのセールス・イネーブルメント実践 「独自講座」と「レベル別ロープレ」
現代における営業組織育成のチャレンジ
営業に必要な戦闘力を定量的・定性的に測定できていることが重要となる
自社の営業メンバーの現在の戦闘力がどのくらいか、マネージャーや首位にの人間はどのくらい理解しているでしょうか。メンバーの戦闘力を定量、定性で把握していることは極めて重要です。
理由として、本人のキャパシティ以上の仕事を振り、能力以上のパフォーマンスを要求することは著しいモチベーションの低下につながるからです。
また、定性的にも営業メンバー一人一人を理解しておくことが重要です。本人の適性や仕事への取り組み方、過去の経験から踏まえたものごとの考え方など、一人一人異なるため、画一的なアプローチは必ず脱落者を生み出します。
営業メンバーの能力を定量的にも定性的に把握することで、最大限に各メンバーの能力を活かすためにはどういったアプローチがいいのか、それこそさまざまなデータを元に分析していく必要があるのです。
以下のような論点について答えられる企業は少ない
チームに必要な能力は何か?
営業メンバーの中にも担当者と理解を深め、徐々に提案を刷り込みボトムアプローチを得意とする営業もいれば、自社の経営層に交渉し、トップアプローチを通し、商談を進めることを得意とする営業がいます。
どちらも正解でどちらが正しいということではなく、マネージャーレベルで自分のチームにはどういった能力のメンバーが現在求められているか、把握できていますでしょうか。
その能力はどういった行動に落ちるのか?
必要な能力がわかると、営業組織や顧客に対し、どういった影響をもたらしてくれるでしょうか。能力が分かり、行動に反映された場合、日々の営業活動にどのように反映されるか、チームを変えてくれるか、十分な考察が必要です。
その行動は、どの程度必要なのか?
今のメンバー構成を踏まえた際、現在のメンバーでは足りない部分が必ずあります。なぜならば完璧な組織はないからです。例えば、自分で学び、周囲の人たちを巻き込んでくれる経験豊かな営業メンバーがいれば、若いチームの場合、いいお手本になるでしょう。
仮にですがそのようなメンバーがどのくらいチームに必要か、なぜ必要なのか、いない場合はどうなのか、さまざまなケースで考察をしておく必要があります。
それらは、JD(職務定義書)に十分記載されているか?
求められる能力はJDに定義されている必要があります。10年以上の営業経験があり、自ら新規顧客を開拓し、新たな販路を作っていくことが求められているのか、経験豊かなメンバーが若手のメンバーに営業の方法を見せながらチーム全体の底上げをして欲しい状態なのか、明記されているとミスマッチがなくなります。
営業マンの各ジョブは定義されているか?
営業メンバーのジョブの定義も極めて重要です。新規しか行わないか、既存顧客が中心かだけでも大きな違いがあります。求められる能力もパーソナリティも全く異なるたるため、自分が何をすべきか、ジョブの定義も重要です。
入社してみて定義されたジョブと異なれば、認識の齟齬から軋轢が生じる可能性があります。JDと異なるジョブをアサインすることは場合によっては早期退職のリスクにもつながるでしょう。
キャリアパスに応じて、各ジョブのレベル感は定義されているか?
JDに納得して入社しますが、入社を考えるメンバーは入社した後の自身のキャリアを提示してもらうだけでモチベーションが上がります。
まずは目の前のジョブに全力を注ぐのはもちろんですが、自身が将来どうなりたいか、キャリアパスがどう描けるかまでを踏まえてジョブを定義してくれていれば、その目標を見据えて行動できるでしょう。
各ジョブのレベルを上げるための、プログラムは用意されているか?
プログラムが用意されているということは、会社としてサポートしますという意思表示であり、メンバーが大切にされているという気持ちになります。
何もかも整っている会社はないですが、イネイブルメントプログラムがあることで、どんなスキルが求められているかのメッセージにもなり、会社としての考え方も理解できます。
人材育成の5つのステップ
具体的には、次の5つのステップで取り組みます。
Step 1. 営業オペレーションの可視化
まずは大枠から営業オペレーションやプロセスを可視化することからはじまります。全体を俯瞰し大枠を見渡すことで、営業が会社にとってどのような位置付けか、どの方向を向いているのか、どういった人材が求められているか明らかになります。
採用や育成を進める上では他にも会社の歴史、考え方、競合との差別化、カルチャーなど総合的に理解を深めます。その中で、営業オペレーションにまで落とし込み、どういったスキルを持った社員が必要で、どのような人が売り上げに貢献してくれるかを定義します。
Step 2. 各営業担当者の成果の可視化
営業オペレーションが見えたところで、次は各営業担当者の成果に関して可視化していきます。通常自社の営業担当者はどのように動いているのか、他の部門のメンバーとどう関わるのか、顧客とどのような折衝を行い、提案を進め、契約を勝ち取っているのかについて理解していきます。
普段の営業担当者のオペレーションや成果がわかってくると、どのようなスキルやパーソナリティを持った人が自社にとって適切な人材かが見えてきます。
顧客や自社ソリューションの特徴なども理解が深まれば深まるほど、動き方や活動量、営業組織の実態が見えてくるでしょう。
Step 3. 理想的な営業担当者の特徴の抽出
営業の担当者レベルまで可視化できると、活躍できる営業担当者の特徴も見えてきます。この会社で活躍するためにはどんなスキルが必要で、トップセールスに共通するスキルや考え方が見えてきます。
たくさんの営業担当者のデータがあればあるほど、自社で活躍できるセールスの特徴が確からしくなるでしょう。
それは同時に、活躍できない社員の特徴を抽出することもできるようになります。したがって、採用や育成の時点で、そのような傾向があれば採用を見送ったり、改善できるようなプログラムを組み、売れる営業になるよう支援を続けていきます。
Step 4. スキルレベルの可視化
具体的にトップセールスの特徴やスキルやパーソナリティが見えてきたら、スキルレベルにまで可視化を行います。
顧客への反応スピードが早い、社内のメンバーを巻き込む能力が高い、逆算思考があり、どんどん商談を進めていける、困ったタイミングでいち早く相談に来るなどなど、様々です。
それらのスキルを抽象化していき、どういった能力が向上すればトップセールスのケイパビリティを備えることができるか、スキルレベルを磨いていくのです。
事業目標から逆算する目標水準
Step 5. 採用・育成プロセスの改善
営業オペレーションの全体像が分かり、ここの営業が分かり、さらにトップセールス、結果を出せないセールスの動きが見えてくると、採用や育成プロセスをどのように改善していけばいいか答えが見えてくるはずです。
どんな人材を採用すべきか、トップセールス輩出するためにはどのような育成プロセスを敷くべきか、将来的にもキャリアパスをどのように示せるか。さまざまな状況を踏まえた上で、
まとめ
新しい行動様式が変わり、デジタル化の波が押し寄せています。結果として新しい営業スタイルへシフトしてきております。営業は会社の売上につながる日々の活動をしており、とても重要な役割を果たしています。多くの企業が採用や営業組織の育成に関心があるとも答えているように、営業組織の強化は重要になっています。
そこで、営業組織に関するテコ入れが始まっており、育成やイネーブルメンとが注目されています。本記事では育成・イネーブルメントの重要性、事例について触れ、なぜ取り組むべきかがお分かりいただけたかと思います。
ただし、営業組織を強化することは簡単ではなく、データを活用した営業組織の強化が求められています。その際は定量的なデータを取ることはもちろんですが、定性的に営業メンバーの分析を同時に行うことも大切です。
最終的に強い組織を作るためには、人材育成について5つのステップで営業オペレーションを把握するところから営業メンバーの分析、必要なスキルセットは何かまで落とし込み、自社にとって必要なスキルを持つ社員の採用や育成を強化していくことが重要になります。
以下資料では、Magic Moment がこれまで営業組織をご支援したきたノウハウを生かし、データを活用した営業組織の育成について体系的にまとめています。
無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいませ。
Accel の記事や、セミナーの告知、公開したホワイトペーパーなど、サブスクリプションビジネスの成功に役立つ情報を定期的にお届けします。